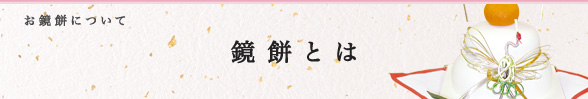
鏡餅の意味 |
| 神様への供物である鏡餅の形は三種の神器の一つで”知”をもって世の中を治める道具とされた銅鏡の形からきたとも、人間の心臓の形を型どったものといわれています。 上下一体となった形は”お日さま”と”お月さま”をあらわしており、一年という年を めでたく重ねるという意味が込められているとも伝えられます。 |
 |
鏡餅はいつ飾るか |
| 28日〜30日がよいとされています。また、31日は「一夜飾り」といって葬儀の準備を連想させるということで好まれません。29日は9がつくことで「苦立て」といって避けられていましたが、29を福(ふく)とみたてて、縁起が良いと考えることもあるようです。少し早めに飾って、過ぎ行く年、新しい年への感謝をこめてはいかがでしょうか。→いつ下げるかは鏡開きを御覧ください。 | 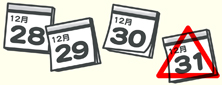 |
鏡餅はどこに飾るか |
| 鏡餅は室町時代以降は床の間のある書院造りが普及したため、原則として床の間に飾っていたようですが、現在では飾る家や会社の「主たる場所」(神棚、台所、仕事机…等)にお供えするのが基本になっているようです。 |  |
鏡餅と注連縄(しめなわ)の関係 |
| お正月のはじまりは、先祖の御霊を祀る行事ー魂祭ーだったといわれています。その精進は万物の霊に感謝し、 家々に注連縄を張って歳神さまをお迎えし、新しい年の生命をいただいて子孫繁栄を願うという形で現代へ受け継がれてきました。 稲の実であるお米で鏡餅をつくり歳神さまへの供物とし、その茎である藁で作った注連縄を家々に張り神聖化 するのも、日本人の神への感謝と新しい年への願いのあらわれといえましょう。 ※注連縄…注連縄の注連は、聖域への魔物の侵入を防ぐ結界のしるし。門松で迎えた歳神さまのいる聖域な区域を示す張り縄です。結界・・・外道・魔物を防いで、その中に入れさせない境界をあらわしています。 |
 |
鏡餅は喪中に飾ってもよいか |
| お正月は先祖の御霊を祀ることからはじまり、その年の福徳を司る神様、歳徳神様をお迎えする行事です。 新しい年への健康や幸せ、繁栄を祈ることは生きていく上で大切な事です。喪中の時は、鏡餅・門松などのお正月飾りは差し控えた方がよいと言われていますが、福徳を与えてくださる神様への供物である鏡餅ですから、新年の福徳のお願いを込めてぜひ供えてください。 ただし、忌中と呼ばれる間の場合は、飾るのをやめた方がよいでしょう。 ※忌中…近親者の喪に服して忌み慎んでいる期間。一般的には死後49日間のこと。 |
 |



